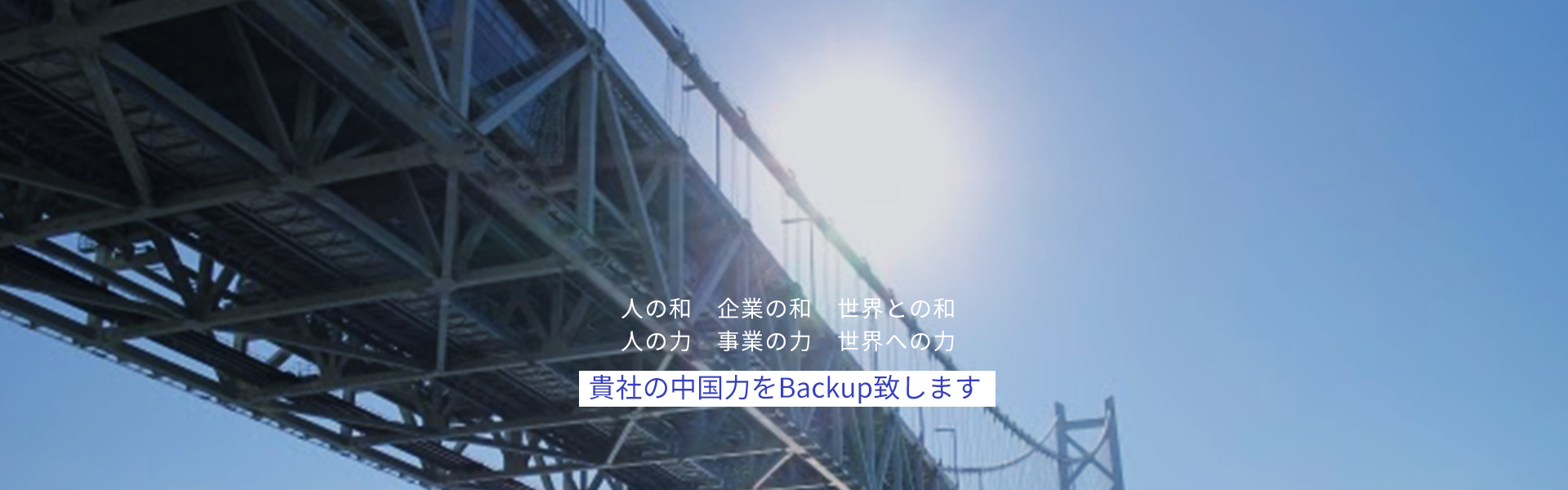中国人の「癖」&日本人の「根性」 ~酒後に徳を見る中国人と無礼講で羽目を外す日本人
ビジネス出張や友好訪問問わず、「中国人の乾杯にやられた」日本人は多い。
知人は20年前に茅台酒に付き合った挙句、肝臓がやられ帰国後2週間も入院した。「そこまで飲んだのに、中国人はなぜ酔っぱらわないのか」と、氏は今でもショックを隠せず首をかしげる。
さて、むしゃくしゃ乾杯する中国人はなぜ酔っ払いが少ないのか?「酒後無徳」になってはならないと、考えているからである。人々はこのことを飲酒時の最低ラインとして守り、また言わずもがなの掟として社会的に認識されている。
酒を飲んだ後は本性が見える、と日本でも言われるが、中国では「人に無礼なことを言ったり、或は戯れ言を言ったり」するのは、「最終的には信用に値しない」、「いざという時には失敗する」と思われる。まして大騒ぎして周りに迷惑をかけるなんていうことはもってのほか。つまり、中国人は酒豪を敬うが、「酒後無徳」の人を軽蔑するのである。
とはいっても、「徳」を見せかけるために、飲むのを拒んだり、避けたりするのも評価されない。胸襟を開いて豪快に飲むのは「和」であり、迫られて或は調子に乗って飲み過ぎてしまうのは「同」である。君子はあくまでも「和して同せず」でなければならない。だから、酒は飲む人の品格を表すものだと、中国人は考える。かの諸葛孔明が酒後の振る舞いを観察し人事を決めていたことも知られているように、今でも、「酒後無徳」で昇進を逃した人は多い。
さて、日本人の「無礼講」を見てみよう。「あの大会社の社長は酒を飲むと、部下との上下関係をまったく気にせず振る舞う」、「日本の宴席では女性に失礼なことを言ったりひどい場合手を出したりするのも許されるのか」、「夜の繁華街には酔っ払いがすごく多い」と、逆に酒後の日本人を見て驚きを隠せない中国人は少なくないだろう。
「飲みニュケ―ション」という組織文化を知らない中国人なら、日本人は「酒後無徳」と決めつける。なお、上下遠近を気にせず、羽目を外してしまう「無礼講」を知っていたら、彼らは絶句するだろう。
酒はコミュニケーション促進剤である。同時に人々の考え方や物事の掟を知る手段でもある。時には相手の視点から酒を考えて振る舞うといいと思う。