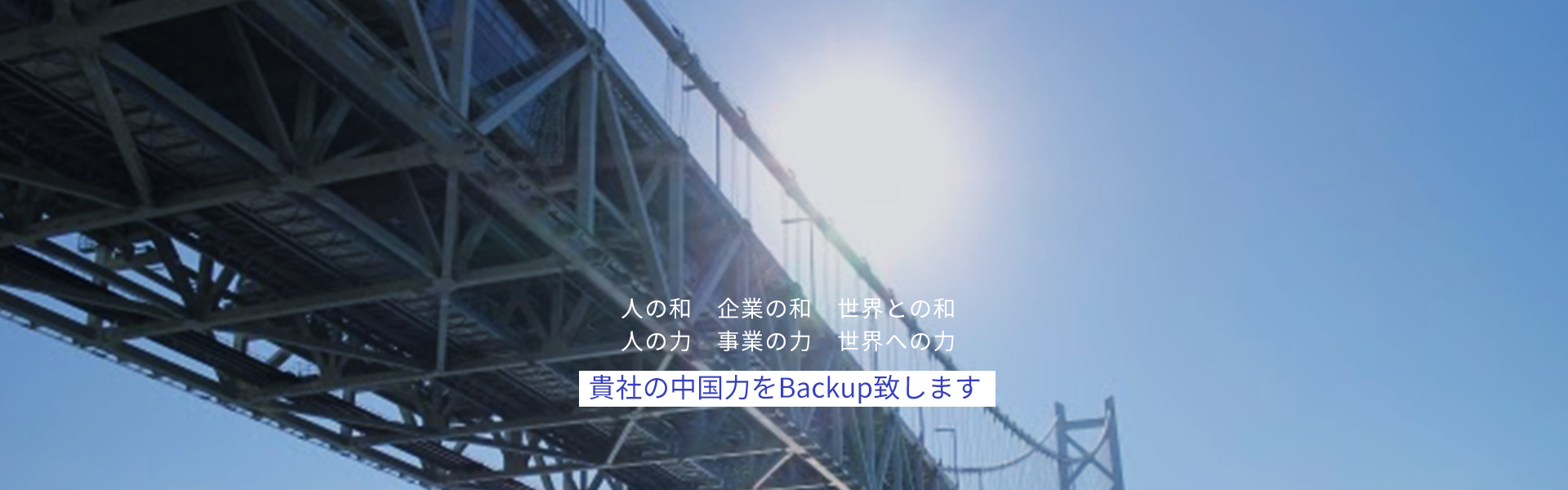中国人の「癖」&日本人の「根性」 ~すぐ謝る日本人と絶対に謝らない中国人
日本人と接した中国人なら、恐らく誰でも日本人の素早い謝り方に感心する。
例えば、朝の通勤ラッシュにちょっとぶつかったりすると、ほぼ同時に両方から「ごめんなさい」と聞こえるだろう。 先にぶつけた人も、ぶつけられた人も、この優しい「ごめんなさい」の一言で、互いが一瞬にして和む。
さて、このシーンは中国だったらどうなるだろうか。 個人差があるものの、男女老若問わず、血が上って口喧嘩し、ときには周りを巻き込んで激しい「論争」に発展してしまうだろう。 喧嘩や論争の中身を覗いて見ると、たいてい「どちらが先に相手にぶつけたか」、「ぶつけられた方にも非がなかったか」、「故意的行為かどうか」などがぎっしり詰まっている。 ようするに、 「 事件」の原因をこまめに分析し、白黒をはっきりさせるために、必死に「講理」(=理を論ずる)して周囲の賛同を得ようとする。 「理」にかなっていたら、相手に損害を与えても悪くない。 周囲も「理」を論じた結果をみて見方を決める。
つまり、中国人にとっては、 謝ることは即ち非を認めること、非を認めることは弁償や損することになりかねないという死活問題だ。 ところで世の中には理不尽なこと、つまり「理」のはっきりしないことが多い。 そこで、中国人は明かに自分に「理」のないことには素直に謝るが、「理」のある部分が少しでも絡むと、その「理」が認められるまでは一歩も譲らず、絶対に謝らない。 交通事故同士は、たいした事故でもないのに、渋滞を引き起してでも、警察の前で「講理」できるように現場を確保するような風景も大体この原因にある。
一方、すぐに謝る日本人は、礼儀正しく協調精神に富むようにみえるが、中国人に言わせれば、「そんな謝り方は誰だってできる」という。 なぜならば、日本人にとっては、謝ることの多くが非を認めることにはイコールしない。 むしろ「真摯な態度で周囲の同情を得てことを済ませようとする」本質がある。 謝ることは非を認めることとは違うので、謝っても何のリスクもなく、回数が多いほど、また態度が真摯なほど自分に有利になる。 だから、ことの是非と関係なく、我先に真摯に謝るのだ。 企業による不祥事をみても、深々と謝る経営者たちは真摯な態度を示しながらも、不正を隠し、非を認めようとしない。 「民意」もその態度に左右されるため、ことが曖昧なうち済まされてしまう。
物事には本質も形も必要。 謝ることも同様だ。 このことを重んずれば、相互理解はしやすくなるだろう。